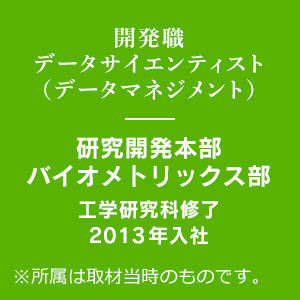障害による仕事や
キャリアの不安を
自らの工夫と
周囲の協力で克服
コミュニケーションを
取りやすい安心な環境
学生時代に再生医療や創薬に用いる細胞画像のデータ解析を研究していたことから、医薬とデータに関わるデータマネジメントの仕事に就きたいと考えていました。協和キリンを選んだのは、以前から興味を持っていた核酸医薬品の研究開発に力を入れている企業だったからです。また、聴覚障害のある私にとっては、説明会や選考の過程で、障害があっても活躍できそうだと確信でき、さらに魅力が深まりました。
私の両耳には常に耳鳴りの症状があり、さらに音が歪んで聞こえます。補聴器を使用して相手の口の形からなんとなく読み取って会話をすることはできますが、早口だったりするとまったくわかりません。このような障害を持つ私が会社に入り、どのように仕事を行っていくのか、就職活動ではその点を一番懸念していました。当社の採用選考では、「どんな仕事をしていくのか」「どこまでできるのか」ということを具体的に相談でき、安心できました。実際に当社に入社して感じるのは、周囲とのコミュニケーションが取りやすく、働き方や先々のキャリアの構築の仕方について継続的に相談できるということ。周囲の方とコミュニケーションをしっかり取れることが、障害をカバーしながら働いていく上で何よりも重要だと認識しました。

さまざまな工夫で
医薬品開発に貢献
私は現在、データマネジメント担当として複数のプロジェクトに参画しています。データマネジメントの仕事ではプロジェクトの各部門やCRO(Contract Research Organization:臨床開発業務をサポートする機関)の担当者と協議をし、やるべきことについて認識を共有していかなければなりません。聴覚に障害を持つ私が、どのように会議に参加すればよいのかという点について、不安を強く感じていたことも事実です。多くの人が参加する会議では、すべての参加者が話す内容を正確に把握することが難しくなります。音声認識ソフト(マイクを通して音声を文字変換する補助ツール)や通訳者を入れることである程度は解決されますが、私としてはただ一方的に情報を受け取るだけでなく、積極的に協議事項の決定に参画したいという想いもありました。
そこで私は、まず事前に会議の目的や構成を確認して、議論がまとまりやすくなるように複数の提案内容やその長短の説明も準備して会議に臨み、さらに参加者には、必ずマイクを通して一人ずつ話してもらうようにお願いしました。そのような働きかけの甲斐もあって、主体的に会議に参加できるようになりました。その他にも、自身の認識に間違いがないよう、会話で決定した内容をその場で復唱し、正しい理解を心がけています。今後の目標としては、自ら先駆けとなって、障害のある人でも新薬開発に貢献できる環境を広げる努力を続けていきたいと思っています。